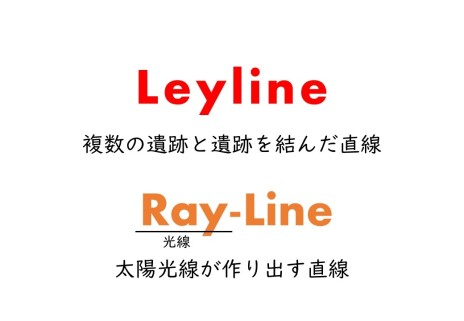レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」~龍と生きるまち 信州上田・塩田平~STORY #093
- ホーム
- ストーリー検索
- レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」
- 信州上田のレイラインとは
2025.02.25
一般
信州上田のレイラインとは
信州上田、長野県上田市の日本遺産『レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」~龍と生きるまち 信州上田・塩田平~』は、タイトルに「レイライン」「聖地」「龍」といった超常的で神聖なキーワードが散りばめられていることからも見て取れるように、人智を超えた存在に対する畏敬崇拝、『祈り』といった信仰を中心としたストーリーです。
中でも「レイライン」とは何か?
というところが一番気になるのではないでしょうか?
今回は信州上田の「レイライン」からストーリーを深堀したいと思います。
中でも「レイライン」とは何か?
というところが一番気になるのではないでしょうか?
今回は信州上田の「レイライン」からストーリーを深堀したいと思います。
『レイライン』
カタカナで表記していますが、アルファベットにすると「Leyline」「Ray-line」の2通りの表記が可能だと考えられます。
「Leyline」は、複数の遺跡と遺跡を結んだ直線のことを指す造語です。神秘的浪漫、考古学的魅力のひとつとして、古代イギリスの巨石遺跡群を研究する考古学者のアルフレッド・ワトキンズが1921年に提唱した仮説です。
一方の「Ray-line」は、太陽光線(Ray)が作り出す直線(Line)という意味です。
「Leyline」は、複数の遺跡と遺跡を結んだ直線のことを指す造語です。神秘的浪漫、考古学的魅力のひとつとして、古代イギリスの巨石遺跡群を研究する考古学者のアルフレッド・ワトキンズが1921年に提唱した仮説です。
一方の「Ray-line」は、太陽光線(Ray)が作り出す直線(Line)という意味です。
一般的にはLで始まる「Leyline」で語られることが多いレイラインですが、複数の点と点、複数の遺跡と遺跡を結ぶだけであれば無数に直線が作れてしまいますので、これが日の出や日の入りの光の線によって結ぶことができる、あるいはそうした直線と重なるという部分に、稀少価値があり、ゆえに神秘的な部分となります。
日本では、春分や秋分、夏至や冬至といった特別な日の直線と重なることに神秘性が見出されています。
つまり、直線が描けるということだけでなく、LとRの2つのレイラインが重なる、というところに意味があるわけです。
春分や秋分、夏至や冬至といった特別な日に見られる日本のレイラインの一例は図のとおりです。
つまり、直線が描けるということだけでなく、LとRの2つのレイラインが重なる、というところに意味があるわけです。
春分や秋分、夏至や冬至といった特別な日に見られる日本のレイラインの一例は図のとおりです。
上田市のレイラインはと言いますと、まずは太陽への信仰の象徴である大日如来を祀る重要文化財三重塔を有する『信濃国分寺』。
大地への信仰の象徴であり「国土・大地」を御神体とする『生島足島神社』。
雨と水を司る龍神を奉る『女神岳』。
大地への信仰の象徴であり「国土・大地」を御神体とする『生島足島神社』。
雨と水を司る龍神を奉る『女神岳』。
さらに不思議なことに、この夏至の朝日が作り出す「Ray-line」(冬至の夕日が作り出す「Ray-line」)は、「国土・大地」を御神体とする『生島足島神社』の参道と一致し、東西両端にある鳥居の中をくぐり抜けます。
生島足島神社という局地的にも、そして信州上田を貫く大局的にも、レイラインが見て取れます。
生島足島神社という局地的にも、そして信州上田を貫く大局的にも、レイラインが見て取れます。
では、なぜこのような現象が見られるのか。
なぜ「Ray-line」と一致するように参道が設計されたり、『太陽』と『大地』と『水』に関する聖地を結んだ「Leyline」が描けるのでしょうか。
これには、信州上田の気候風土が大きく関係しています。
長野県上田市は、本州で最も雨が少ない地域と言われています。
年間降水量は約900mm。これは全国で最低ランクです。
信州上田・塩田平と呼ばれる盆地では、米づくりに欠かせない水の確保が常に課題でした。そのため、貴重な雨水を無駄にしないように「ため池」の築造が盛んに行われました。最盛期には塩田平の地に数百のため池があったとされています。
現在でも100を超えるため池が残されています。
なぜ「Ray-line」と一致するように参道が設計されたり、『太陽』と『大地』と『水』に関する聖地を結んだ「Leyline」が描けるのでしょうか。
これには、信州上田の気候風土が大きく関係しています。
長野県上田市は、本州で最も雨が少ない地域と言われています。
年間降水量は約900mm。これは全国で最低ランクです。
信州上田・塩田平と呼ばれる盆地では、米づくりに欠かせない水の確保が常に課題でした。そのため、貴重な雨水を無駄にしないように「ため池」の築造が盛んに行われました。最盛期には塩田平の地に数百のため池があったとされています。
現在でも100を超えるため池が残されています。
しかし、このため池も、雨が降らなければ枯れてしまいます。
日照りという災害は、「神の試練」や「神の怒り」などと考えられ、神仏への信仰心を強固なものとしてきました。
「雨が降っても槍が降っても」「雨降って地固まる」などのことわざがあるように、ともすれば「障害」として捉えられる『雨』も、信州上田では『天の恵み』です。
雨水とともに米づくりに欠かせない「太陽の光」「太陽の恵み」とともに、米づくりの成否を最後は「おてんとうさま(お天道様)」に委ねてきました。
レイラインにそって参道を設け、あるいはレイラインに沿って聖地と聖地をつないでいくという仕掛けは、
レイラインに沿う、すなわち、天意に沿う、太陽、お天道様に従うということであり、もしかするとそれは、お天道様に従順な姿勢を示し、怒りを鎮め、恵みを求めるという『祈りの形』ではないでしょうか。
そう思わせるだけの歴史が、太陽と大地に恵まれ龍とともに生きる上田・塩田平の地には眠っているのです。
日照りという災害は、「神の試練」や「神の怒り」などと考えられ、神仏への信仰心を強固なものとしてきました。
「雨が降っても槍が降っても」「雨降って地固まる」などのことわざがあるように、ともすれば「障害」として捉えられる『雨』も、信州上田では『天の恵み』です。
雨水とともに米づくりに欠かせない「太陽の光」「太陽の恵み」とともに、米づくりの成否を最後は「おてんとうさま(お天道様)」に委ねてきました。
レイラインにそって参道を設け、あるいはレイラインに沿って聖地と聖地をつないでいくという仕掛けは、
レイラインに沿う、すなわち、天意に沿う、太陽、お天道様に従うということであり、もしかするとそれは、お天道様に従順な姿勢を示し、怒りを鎮め、恵みを求めるという『祈りの形』ではないでしょうか。
そう思わせるだけの歴史が、太陽と大地に恵まれ龍とともに生きる上田・塩田平の地には眠っているのです。