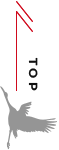「百世の安堵」〜津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産〜STORY #063
テーマ
- 海・水辺
- 森・木
- 祭礼
時代
- 江戸
ストーリーSTORY
広川町の海岸は、松が屏風のように立ち並び、
見上げる程の土盛りの堤防が海との緩衝地を形づくり、
沖の突堤、海沿いの石堤と多重防御システムを構築しています。
堤防に添う町並みは、豪壮な木造三階建の楼閣がそびえ、
重厚な瓦屋根、漆喰や船板の外壁が印象的な町家が、
高台に延びる通りや小路に面して軒を連ね、
避難を意識した町が築かれています。
江戸時代、津波に襲われた人々は、復興を果たし、
この町に日本の防災文化の縮図を浮び上らせました。
防災遺産は、世代から世代へと災害の記憶を伝え、
今も暮らしの中に息づいています。
見上げる程の土盛りの堤防が海との緩衝地を形づくり、
沖の突堤、海沿いの石堤と多重防御システムを構築しています。
堤防に添う町並みは、豪壮な木造三階建の楼閣がそびえ、
重厚な瓦屋根、漆喰や船板の外壁が印象的な町家が、
高台に延びる通りや小路に面して軒を連ね、
避難を意識した町が築かれています。
江戸時代、津波に襲われた人々は、復興を果たし、
この町に日本の防災文化の縮図を浮び上らせました。
防災遺産は、世代から世代へと災害の記憶を伝え、
今も暮らしの中に息づいています。
広川町は、起伏なす紀伊山脈が海に迫り、複雑な海岸線には岩礁と円弧を描く砂浜が点在し、沖には小島が連なる変化に富んだ風景があり、豊かな自然に育まれてきました。海沿いには、幹を伸ばした松が、弓状に緑を描いて並んでいます。昼も日差しが通らぬほど生い茂った松並木の向こうに、見上げるような土の堤防と背丈ほどの石垣が、町を覆い包んでいることに気付きます。土で固めた堤防に上ると、なだらかに裾の広がっている小山のような印象を受けます。
「稲むらの火」
この町は、江戸と大坂を結ぶ廻船や熊野参詣道の要所として隆盛の一途をたどりましたが、深く切れ込んだ湾の最深部に位置し、さらに低地であるため、その繁栄は津波の危機と背中合わせでした。
江戸時代末期、1854年(安政元年)11月5日、突如地震が発生し、やがて暗闇の町に津波が襲ってきました。津波を察知した濱口梧陵は、田の稲むらに火を放ち、高台の寺社に逃げる人々の明かりとし、多くの命を救いました。その後、寺社は、蔵の貯蔵米を炊き出して避難民を飢えから救うなど、濱口梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました。
この出来事は、明治の文豪小泉八雲(Lafcadio Hearn)によって「生ける神(ALiving God)」として世界に発表され、その後「稲むらの火」のタイトルで小学校の教科書にも掲載されています。
江戸時代末期、1854年(安政元年)11月5日、突如地震が発生し、やがて暗闇の町に津波が襲ってきました。津波を察知した濱口梧陵は、田の稲むらに火を放ち、高台の寺社に逃げる人々の明かりとし、多くの命を救いました。その後、寺社は、蔵の貯蔵米を炊き出して避難民を飢えから救うなど、濱口梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました。
この出来事は、明治の文豪小泉八雲(Lafcadio Hearn)によって「生ける神(ALiving God)」として世界に発表され、その後「稲むらの火」のタイトルで小学校の教科書にも掲載されています。
 左:高台の神社(広八幡神社)/右:稲むら(稲束を積み重ねたもの)
左:高台の神社(広八幡神社)/右:稲むら(稲束を積み重ねたもの)
まちの復興に向けて
津波襲来で被害を受けた人々は、町の行く末を案じて町を離れようとしていました。その様子を見ていた濱口梧陵は、津波が沖の突堤と波打ち際の石堤を乗り越え町を襲ったことから、抜本的な対策のため、新たな堤防の築造を計画しました。濱口梧陵は『築堤の工を起して住民百世の安堵を図る』と述べ、復興の象徴として築堤に力を注ぎました。4年の歳月をかけ、山から土を運び、突き固めた堤防の高さは5m、長さは600mにも及びます。堤防は津波の衝撃を弱めるために湾曲し、港から町への避難を容易にするため、斜面を緩やかに築いています。さらに、堤防の前面には、津波で町に漁船が流れ込まないように、松を1,000本植え、堤防の補修費用を賄うために蝋燭の材料となる櫨を100本植えました。
堤防築造に要した費用は、濱口梧陵が私財を提供しました。作業には、大人から子どもまですべての人々が参加し、その日のうちに賃金が支払われたため、被災した人々は安心して暮らしを続けることが出来ました。そして、濱口梧陵は荒廃した田畑を復旧し、漁夫には漁船を買い与え、被災した陶器産業に援助を行うなど、産業の復興にも献身的に取り組みました。
人材育成にも尽力していた濱口梧陵は、津波で被災した私塾を憂い再興し、永続を願って「耐久社」と名付けました。耐久社は、耐久中学校に受け継がれ、今も濱口梧陵の教えを子どもたちに伝えています。復興にあたって、濱口梧陵が結成を呼び掛けた自警団「広村崇義団」も活躍し、被災した人々を支援しました。
堤防築造に要した費用は、濱口梧陵が私財を提供しました。作業には、大人から子どもまですべての人々が参加し、その日のうちに賃金が支払われたため、被災した人々は安心して暮らしを続けることが出来ました。そして、濱口梧陵は荒廃した田畑を復旧し、漁夫には漁船を買い与え、被災した陶器産業に援助を行うなど、産業の復興にも献身的に取り組みました。
人材育成にも尽力していた濱口梧陵は、津波で被災した私塾を憂い再興し、永続を願って「耐久社」と名付けました。耐久社は、耐久中学校に受け継がれ、今も濱口梧陵の教えを子どもたちに伝えています。復興にあたって、濱口梧陵が結成を呼び掛けた自警団「広村崇義団」も活躍し、被災した人々を支援しました。
防災が息づくまち
港から堤防の切通しの門をくぐると、ゆっくり坂を上り丘の寺社に至る道が開き、道と交差する通りに沿い町並みが広がります。堤防に寄り集まるその町並みは、銀の鱗を並べたように重厚な瓦屋根が連なり、漆喰や船板の外壁、窓を飾る格子の意匠が特徴的です。町並みを見廻すと、漆喰の大壁が立ち上り、入母屋造に紀州特有の丸桟瓦の屋根を葺いた、黒銀色の屋根瓦と白い漆喰のコントラストが印象的な木造三階建の建物がひときわ目立ちます。町並みに浮かび上がる「御風楼」と名付けられたこの建物は、城のような大 規模な迫力と風格を備え、内部には折上格天井などの瀟洒な意匠をあしらい、三階の座敷は海のパノラマを借景として取り入れています。
御風楼は、地元の大工たちの高い技術力を結晶化させた最高峰の建築物です。安政津波の経験を活かし、耐震性を高める工夫も施し、柱の支えは、明治期の建物には珍しく鉄製の器具を用いています。安政津波の惨状を目の当たりにした当主の濱口吉右衛門は、濱口梧陵の堤防築造に協力するとともに、町の人々のために、迎賓施設としての役割以外に、津波災害時の避難機能を備えた御風楼の建設を手掛けました。
安政の津波は、町の両脇に流れる川を遡り、高台をめざし川沿いの道を逃げる人々を襲いました。被災後、人々は、麓の町から高台に避難する経路は、町の中央を貫き高台の寺社に延びる「大道」が安全であることに気付きました。町の復興にあたって、大道を避難経路の軸に据え、町並みの通りや小路を結び付け、津波避難を考慮した町づくりを計画し、町の再建を進めました。大道が繋がる堤防の切通しには陸閘門「赤門」を設け、防御機能も拡張しました。
安政津波の避難場所となった 広八幡神社 には、古くから「津波には、ただ足早に宮参り」と言い伝えがあります。被災後、広八幡神社は、犠牲者の鎮魂と町の活性化を祈願し、神楽を舞い、餅撒きを執り行うなど、復興をめざす人々を励まし元気づけました。広八幡神社は今も崇敬を集め、暮らしと結びついた避難場所として人々に意識されています。
1946年(昭和21年)には、再び地震が発生し、夜明け前の町を津波が襲いました。堤防は津波の流入を防ぎ、人々は、燃える稲むらを明かりに大道を逃げ、高台の寺社と御風楼の三階に避難しました。防災遺産は町と人々の命を津波から守り、安政の津波から復興した町の姿を今に伝えています。
御風楼は、地元の大工たちの高い技術力を結晶化させた最高峰の建築物です。安政津波の経験を活かし、耐震性を高める工夫も施し、柱の支えは、明治期の建物には珍しく鉄製の器具を用いています。安政津波の惨状を目の当たりにした当主の濱口吉右衛門は、濱口梧陵の堤防築造に協力するとともに、町の人々のために、迎賓施設としての役割以外に、津波災害時の避難機能を備えた御風楼の建設を手掛けました。
安政の津波は、町の両脇に流れる川を遡り、高台をめざし川沿いの道を逃げる人々を襲いました。被災後、人々は、麓の町から高台に避難する経路は、町の中央を貫き高台の寺社に延びる「大道」が安全であることに気付きました。町の復興にあたって、大道を避難経路の軸に据え、町並みの通りや小路を結び付け、津波避難を考慮した町づくりを計画し、町の再建を進めました。大道が繋がる堤防の切通しには陸閘門「赤門」を設け、防御機能も拡張しました。
安政津波の避難場所となった 広八幡神社 には、古くから「津波には、ただ足早に宮参り」と言い伝えがあります。被災後、広八幡神社は、犠牲者の鎮魂と町の活性化を祈願し、神楽を舞い、餅撒きを執り行うなど、復興をめざす人々を励まし元気づけました。広八幡神社は今も崇敬を集め、暮らしと結びついた避難場所として人々に意識されています。
1946年(昭和21年)には、再び地震が発生し、夜明け前の町を津波が襲いました。堤防は津波の流入を防ぎ、人々は、燃える稲むらを明かりに大道を逃げ、高台の寺社と御風楼の三階に避難しました。防災遺産は町と人々の命を津波から守り、安政の津波から復興した町の姿を今に伝えています。
防災意識の継承
11月5日の早朝、町の人々は各々堤防に土を盛り、その後津波被害者を追悼する一連の祭礼を、毎年欠くことなく続けています。その昔、早朝から町の人々が総出で近くの山の中腹から土をとり、大人は荷車や畚で、子どもは木綿の風呂敷に入れて堤防まで運び、堤防を補修した後に神事を執り行いました。人々は、先人の警鐘を、暮らしに息づく「祭り」として受け継いでいくことが、防災意識の風化を防ぎ、災害時には大きな力を発揮すると思い、町の伝統行事として絶やさず守ってきました。100年以上積み重ねてきたこの祭礼を「津浪祭」と呼んでいます。
町の人々は、災害の記憶を繋いでいくため、津波防災の心得や先人の警鐘を刻んだ石碑を建てています。神社と堤防に設けられた碑は、「津浪祭」や神社の秋祭りで人々に意識され、世代を越えて連綿と受け継がれています。神社の碑には、濱口梧陵と親交のあった勝海舟が「田の稲むらに火を付けて明かりにし、多くの人々を救った」と碑文を刻み、その偉業が今もうかがわれます。町を巡り歩くと、災害の実情を後世に伝えるため、津波の高さを刻む建物にも出会います。「安政の津波ここまで上がる、後日のために記す。」と記録された柱からは、伝承することの重要性が感じ取れます。
町の人々は、災害の記憶を繋いでいくため、津波防災の心得や先人の警鐘を刻んだ石碑を建てています。神社と堤防に設けられた碑は、「津浪祭」や神社の秋祭りで人々に意識され、世代を越えて連綿と受け継がれています。神社の碑には、濱口梧陵と親交のあった勝海舟が「田の稲むらに火を付けて明かりにし、多くの人々を救った」と碑文を刻み、その偉業が今もうかがわれます。町を巡り歩くと、災害の実情を後世に伝えるため、津波の高さを刻む建物にも出会います。「安政の津波ここまで上がる、後日のために記す。」と記録された柱からは、伝承することの重要性が感じ取れます。
2015年(平成27年)には国連で11月5日が「世界津波の日(World Tsunami Awareness Day)」として制定されました。津波防災にとって重要な要素は、「素早く明快に危機を知らせること」「より良い復興を目指すこと」「言い伝えや祭りの伝える力を活用すること」です。広川町には、この三つの要素が今も息づき、人々は11月5日にあらためて防災を意識してきました。
広川町は、100年先を見据えた防災遺産と防災文化を受け継ぐ人々の英知ある活動が一体となり、現在もその姿を留めています。この地での暮らしを続けていくために、人々が懸命に築き上げた防災遺産は、濃く彩られた歴史を湛え、そこにはこの町の未来を切り拓く文化が息づき、訪れた人に深い感銘を与えます。
広川町は、100年先を見据えた防災遺産と防災文化を受け継ぐ人々の英知ある活動が一体となり、現在もその姿を留めています。この地での暮らしを続けていくために、人々が懸命に築き上げた防災遺産は、濃く彩られた歴史を湛え、そこにはこの町の未来を切り拓く文化が息づき、訪れた人に深い感銘を与えます。
| 【「百世の安堵」 関連情報サイト】 |
|---|