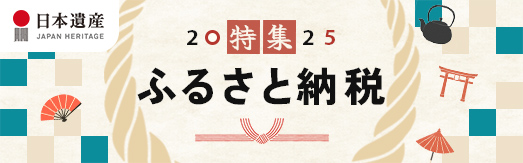「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜STORY #006
みどころspot
-

鵜飼でおもてなし ー鵜匠家の暮らしと祭事ー
長良川鵜飼ミュージアムが所在する鵜飼屋地区には、6件の鵜匠の家が存在しており、その暮らしぶりを垣間見ることができます。
各鵜匠家には主屋のほか、鵜の世話や漁の運営に必要な鳥屋(とや)、水場、松小屋などが設けられています。鵜は、鵜匠にとって一緒に仕事をする大切な相棒で、毎日欠かさず鵜に触れて体調を管理し、獣医による健康診断も行われます。
また鵜飼にまつわる祭事として、7月には水難防止と鮎供養を兼ねて行われる長良川まつり、10月には鵜飼閉幕後に鵜供養が実施されています。
関連する構成文化財
・長良川の鵜飼漁の技術【国重要無形民俗文化財】
・鵜匠家【国重要文化的景観】
・鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術【市重要無形民俗文化財】
・長良川まつり・鮎供養続きを読む
-

鵜飼でおもてなし ー観覧船の造船・操船技術ー
岐阜市鵜飼観覧船造船所は、全国唯一の市営の造船所です。岐阜市では、鵜飼の見物客を乗せるために屋根を備えた観覧船の需要が高まり、他の川船と異なる造船技術が発達しました。観覧船の完成には約半年かかりますが設計図面はなく、船大工の経験と技で作られます。また、その観覧船をこの長良川中流域で操るため、河床が川石である環境に合わせ、サオを主体にカイを併用する操船技術が発達しました。
ともに長良川の鵜飼観覧を支える大切な技術です。
関連する構成文化財
・長良川鵜飼観覧船造船技術【市重要無形民俗文化財】
・長良川鵜飼観覧船操船技術【市重要無形民俗文化財】続きを読む
-

鵜飼でおもてなし -船上の遊宴文化-
長良川の鵜飼でお客をもてなすための様々な技術や文化は、今も多くの観覧客を魅了しています。中でも舟遊びのお供として芸舞妓を乗せて楽しむ「船上の遊宴文化」は、鵜飼観覧と一体で育まれてきました。江戸時代には一度下火になりますが近代に再興を果たし、昭和初期には400名もの芸舞妓がいたといわれています。
現在も長良川鵜飼から生まれた小唄「風折烏帽子」などの伝統的な遊興文化が継承されているなど、鵜飼を「観る文化」が息づいています。
関連する構成文化財
・船上の遊宴文化続きを読む
-

まちの名所でおもてなし ー川原町のまちなみー
川湊の近くに発展した川原町地区には、かつて多くの紙問屋や材木問屋が軒を連ねていました。現在も独特の白木の格子が続く美しい町並みが継承されています。
信長公は、楽市楽座の一方で川湊の商人に舟木座の結成を認めるなど柔軟なまちづくりを行い、道三が築いた長良川の水運を基軸とした城下町を国内有数の商業都市へ発展させました。宣教師ルイス・フロイスは町に一万人が住んでいたと記し、賑わいの様子を「バビロン」の混雑と表現しました。 また柴田勝家の邸宅では「食事をするまで帰してもらえなかった」そうで、城下町での手厚いおもてなしぶりが窺えます。
関連する構成文化財
・川原町のまちなみ【国重要文化的景観】
・川原町屋 【国重要文化的景観】続きを読む
-

まちの名所でおもてなし ー御鮨街道と鮎鮨ー
御鮨街道(おすしかいどう)は岐阜の町から南へ延びる古くからの主要道路で、現在も旧紙問屋など多くの店舗が立ち並んでいます。
鵜飼でとれる鮎は、柿と共に古代から美濃の特産品でした。江戸時代になると町にあった御鮨所(おすしどころ)で調製された鮎鮨が、この道を通って江戸の将軍家に献上されたため、御鮨街道と呼ばれるようになりました。文化庁の100年フードにも認定されている鮎鮨は、現在、長良川沿いの一部の旅館・ホテル、店舗で提供されています。
関連する構成文化財
・御鮨街道のまちなみ【国重要文化的景観】
・鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術【市重要無形民俗文化財】続きを読む