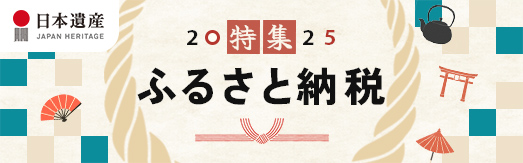「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜STORY #006
みどころspot
-

城下町に息づくおもてなし空間 -川原町屋-
慶長5年(1600)の落城以降、岐阜城には天守がありませんでしたが、明治43年(1910)に復興天守が建設されると、天守が見える位置に座敷を作って、その自慢の眺望で客をもてなすことが、かつての戦国城下町エリアで流行しました。
紙の原料を扱う問屋であった建物は、現在は「cafe&gallery川原町屋」として活用されていますが、2階の座敷からは今も岐阜城復興天守を望むことができます。
関連する構成文化財
・川原町屋 【国重要文化的景観】続きを読む
-

城下町に息づくおもてなし空間 -後楽荘-
慶長5年(1600)の落城以降、岐阜城には天守がありませんでしたが、明治43年(1910)に復興天守が建設されると、天守が見える位置に座敷を作って、その自慢の眺望で客をもてなすことが、かつての戦国城下町エリアで流行しました。
ろうそく・油商の隠居所として建てられた建物は、現在は日本料理店として使用されています。主屋は明治末から大正期にかけて建設されたとされており、庭園からは金華山と復興天守を望むことができます。
関連する構成文化財
・後楽荘 【国重要文化的景観】続きを読む
-

城下町の繁栄を支えた文化 -岐阜大仏-
楽市楽座や長良川の水運で栄えた信長公の岐阜城下町では、長良川上流から運ばれた和紙や竹などを用いた文化が育まれました。その文化は廃城後もさらに洗練され、江戸時代になると岐阜提灯・岐阜団扇・岐阜和傘等の工芸品が知られるようになるほか、江戸時代後期になると日本最大の漆箔の大仏である岐阜大仏を生み出すなど、まちにさらなる賑わいをもたらしました。
正法寺の岐阜大仏は、材木や竹、和紙等を使って大仏殿と一体で造られており、町のランドマークになっています。
関連する構成文化財
・籠大仏 附 木造薬師如来坐像【県重要文化財】
・正法寺大仏殿【市重要文化財・国重要文化的景観】続きを読む
-

城下町の繁栄を支えた文化 -伝統工芸品-
楽市楽座や長良川の水運で栄えた信長公の岐阜城下町では、長良川上流から運ばれた和紙や竹などを用いた文化が育まれました。
岐阜の団扇は室町時代に宮中に献上されていたとの記録があり、岐阜提灯は現在も日本有数の産地となっています。また岐阜和傘は、江戸時代に下級武士の内職として奨励されたことにより地場産業としての基礎が確立され、現在もJR岐阜駅南側の加納地区を中心に伝統の技が受け継がれています。
関連する構成文化財
・岐阜提灯【国伝統的工芸品】
・岐阜提灯の製作用具及び製品【国登録有形民俗文化財】
・岐阜渋うちわ【県郷土工芸品】
・岐阜和傘【国伝統的工芸品】続きを読む