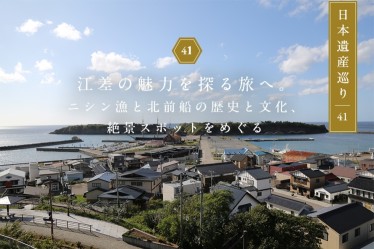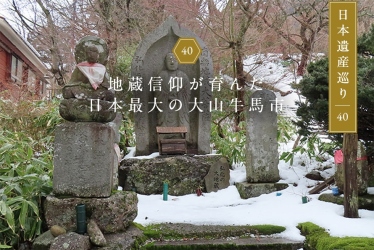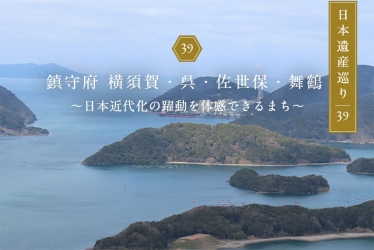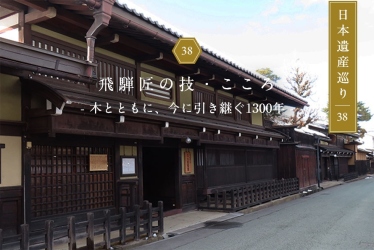六根清浄と六感治癒の地~日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉~STORY #012
テーマ
- 海・水辺
- 森・木
- 祭礼
時代
- 平安
- 鎌倉
- 室町
- 安土
- 明治
ストーリーSTORY
三徳山(みとくさん)は、
山岳修験の場としての急峻な地形と
神仏習合の特異な意匠・構造を持つ
建築とが織りなす独特の景観を有しており、
その人を寄せ付けない厳かさは
1300年にわたって
畏怖の念を持って守られ続けている。
参拝の前に心身を清める場所として
三徳山参詣の拠点を担った
『三朝(みささ)温泉』は、
三徳山参詣の折に白狼により示された
との伝説が残り、
温泉発見から850年を経て、なお、
三徳山信仰と深くつながっている。
今日、三徳山参詣は、
断崖絶壁での参拝により
「六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)」を清め、
湯治により
「六感(観、聴、香、味、触、心)」を癒すという、
ユニークな世界を具現化している。
山岳修験の場としての急峻な地形と
神仏習合の特異な意匠・構造を持つ
建築とが織りなす独特の景観を有しており、
その人を寄せ付けない厳かさは
1300年にわたって
畏怖の念を持って守られ続けている。
参拝の前に心身を清める場所として
三徳山参詣の拠点を担った
『三朝(みささ)温泉』は、
三徳山参詣の折に白狼により示された
との伝説が残り、
温泉発見から850年を経て、なお、
三徳山信仰と深くつながっている。
今日、三徳山参詣は、
断崖絶壁での参拝により
「六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)」を清め、
湯治により
「六感(観、聴、香、味、触、心)」を癒すという、
ユニークな世界を具現化している。
目次
六根清浄と六感治癒の地
神話のふるさと因幡国、出雲国と隣り合う伯耆国に修験道の聖地三徳山が誕生する。この誕生は、修験道の開祖役小角が「神仏のゆかりのあるところへ落としてください。」と三枚の蓮の花びらを空に投げ上げると、そのうちの一枚が伯耆国三徳山へ舞い降り、この地に修験道の行場が開かれたという、「蓮の花びら伝説」として現在も語り継がれている。
その後、三徳山は慈覚大師が山下に堂宇を建立し、「釈迦如来」「阿弥陀如来」・「大日如来」の三尊を安置した三佛寺によって天台密教の道場として隆盛を極めることとなる。
修験道の聖地三徳山への道は、大きく3つに分かれる。東は因幡から、南は美作から、西の出雲からの道である。それぞれの道程には温泉があり、三徳山と温泉は密接な関係を窺うことができる。とりわけ、出雲からの道は三朝温泉を経由し三徳山に入山する道で、歴史的にも最もよく使われた参詣道である。
三朝温泉に残る「白狼伝説」によると、源義朝の家来大久保左馬之祐が、主家再興の祈願のため三徳山に参る道中、楠の根元で年老いた白い狼を見つけた。「お参りの道中に殺生はいけない」と見逃してやったところ、妙見菩薩が夢枕に立ち、白狼を助けた礼に、「かの根株の下からは湯が湧き出ている。その湯で人々の病苦を救うように」と源泉のありかを告げたという。こうして「万病を癒やす湯」として、「株湯」が現代に伝わる。
その後、三徳山は慈覚大師が山下に堂宇を建立し、「釈迦如来」「阿弥陀如来」・「大日如来」の三尊を安置した三佛寺によって天台密教の道場として隆盛を極めることとなる。
修験道の聖地三徳山への道は、大きく3つに分かれる。東は因幡から、南は美作から、西の出雲からの道である。それぞれの道程には温泉があり、三徳山と温泉は密接な関係を窺うことができる。とりわけ、出雲からの道は三朝温泉を経由し三徳山に入山する道で、歴史的にも最もよく使われた参詣道である。
三朝温泉に残る「白狼伝説」によると、源義朝の家来大久保左馬之祐が、主家再興の祈願のため三徳山に参る道中、楠の根元で年老いた白い狼を見つけた。「お参りの道中に殺生はいけない」と見逃してやったところ、妙見菩薩が夢枕に立ち、白狼を助けた礼に、「かの根株の下からは湯が湧き出ている。その湯で人々の病苦を救うように」と源泉のありかを告げたという。こうして「万病を癒やす湯」として、「株湯」が現代に伝わる。
しかしある時、株湯に祀られていた神様を誤って湯の中に落としたため、「一たび湯に入れば、大熱を発し、または気絶する者が後を絶たなくなり、悪霊がいる崇りの湯」と恐れられたこともあるが、その悪霊を三徳山にて鎮め、木像の胸中に納めて薬師如来を三朝温泉の守護仏として祀った。その後は「癒やしの湯」として、湯治に来る人々が後を絶たなくなったという。三徳山との強い結びつきを示す話である。
三徳山では眼・耳・鼻・舌・身・意を清める「六根清浄」は、まず、三朝温泉の湯に入り、身を清め、癒し、心を整え、山へ向かう準備を行い、翌朝、三徳山へ入る。その道中、随所に地蔵菩薩が祀られ、また、辻堂に観音菩薩が祀られ、お参りしつつ三徳山へと向かうことから始まる。
かつての三徳山は北面を北座と呼び、南面を南座と呼んでいた。北座では寺院、僧坊が山内に配され、寺院では仏像、写経、読経、座禅、精進料理などで、己の欲や迷いを断ち切り、心身を清める六根清浄を深めていた。さらに修験道のそれは、深山にわけ入り、洞窟、岩屋で寝食し修行を行っていた。
かつての三徳山は北面を北座と呼び、南面を南座と呼んでいた。北座では寺院、僧坊が山内に配され、寺院では仏像、写経、読経、座禅、精進料理などで、己の欲や迷いを断ち切り、心身を清める六根清浄を深めていた。さらに修験道のそれは、深山にわけ入り、洞窟、岩屋で寝食し修行を行っていた。
今日でも、こうした修験道の一端を「行者道」に垣間見ることができる。行者道は「宿入橋」から始まり、千数百年変わらぬカズラ坂やブナ林の「願掛けの石段」、「馬の背・牛の背」を這いつくばって登り、「文殊堂」、「地蔵堂」など多くの行場を経た後に、突如として眼前に断崖絶壁の岩窟に建つ「国宝投入堂」が現る。
この行者道は、かつての行場を経ることで人と自然界との一体感を強く感じ、自然の力を享受する道として今も残る。
一方、三徳山南座は、現在では地元の人も殆ど訪れない場所であるが、石造物群や行者の墓地とみられる場所など、かつて隆盛を極めた修験道の行場が各所に残っており、三徳山全山が修験道の聖地であったことを物語っている。
先人の行者によって形作られた修験道の聖地において、行を重ね、六根清浄を終えて山を下り、三朝温泉の湯を飲み、浸かり、湯煙に身を置き、再び自然の恵み、自然の力を全身に授かることで、六感を癒す。これをいわゆる、六感治癒と言っている。この「六感治癒」を今に伝える話として、ある人が、目が見えるようになるよう願いを込め、来る日も来る日も行者道に石段を積む行を行い、湯に浸かり身を清めたところ、ある朝、朝日とともに三尊仏が出現し、願がかなえられたという、「願掛けの石段」の物語がある。また、三徳山周辺から切り出した大藤カヅラで行う「三朝の大綱引きジンショ」や、清流三徳川でのカジカの鳴き声や川湯から立ち登る湯煙など、心を癒やす情景の中で六感治癒を果たすことができる。
このように三徳山で「六根」を清め、三朝温泉で「六感」を癒す一連の作法は「人と自然が融合する日本独自の自然観」を特徴的に示したものであり、心と体を洗うことで、誰もが持つ清らかさが蘇る地として、ありつづけている。
一方、三徳山南座は、現在では地元の人も殆ど訪れない場所であるが、石造物群や行者の墓地とみられる場所など、かつて隆盛を極めた修験道の行場が各所に残っており、三徳山全山が修験道の聖地であったことを物語っている。
先人の行者によって形作られた修験道の聖地において、行を重ね、六根清浄を終えて山を下り、三朝温泉の湯を飲み、浸かり、湯煙に身を置き、再び自然の恵み、自然の力を全身に授かることで、六感を癒す。これをいわゆる、六感治癒と言っている。この「六感治癒」を今に伝える話として、ある人が、目が見えるようになるよう願いを込め、来る日も来る日も行者道に石段を積む行を行い、湯に浸かり身を清めたところ、ある朝、朝日とともに三尊仏が出現し、願がかなえられたという、「願掛けの石段」の物語がある。また、三徳山周辺から切り出した大藤カヅラで行う「三朝の大綱引きジンショ」や、清流三徳川でのカジカの鳴き声や川湯から立ち登る湯煙など、心を癒やす情景の中で六感治癒を果たすことができる。
このように三徳山で「六根」を清め、三朝温泉で「六感」を癒す一連の作法は「人と自然が融合する日本独自の自然観」を特徴的に示したものであり、心と体を洗うことで、誰もが持つ清らかさが蘇る地として、ありつづけている。
| 【六根清浄と六感治癒の地 関連情報サイト】 |
|---|