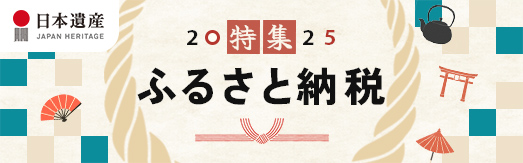構成文化財を探すSEARCH CULTURAL PROPERTIES
- ホーム
- 構成文化財を探す
条件を絞り込む
文化財の名称
概要
-

いわいばし祝橋
- #086 日本ワイン140年史
- 有形文化財
- 登録有形文化財
- 昭和時代以降
- 山梨県甲州市
- 建造物
橋長58.6m 、幅員5.0m、 路肩1.0mのコンクリートアーチ橋で、山梨県内に3橋残るコンクリートアーチ橋のひとつです。
-

きゅうたなかぎんこうしゃおくきゅうたなかぎんこうどぞう旧田中銀行社屋・土蔵
- #086 日本ワイン140年史
- 有形文化財
- 登録有形文化財
- 明治時代
- 大正時代
- 山梨県甲州市
- 建造物
社屋は木造二階建て、桟瓦葺きで、外壁は荒壁の上に灰漆喰で石貼状に仕上げています。また桟瓦には漆喰を盛り、擬洋風建築ら...
-

じぞういんほんどう地蔵院本堂
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 室町時代
- 栃木県益子町
- 建造物
室町時代永正年間(1504~1521)に尾羽寺(おばでら)阿弥陀堂として建てられ、のちに地蔵院と合併し地蔵院本堂となりました。 ...
-

つなじんじゃ(せっしゃおおくらじんじゃふくむ)綱神社(摂社大倉神社含む)
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 室町時代
- 栃木県益子町
- 建造物
綱神社は鎌倉時代、建久5(1194)年に創建しました。現社殿は大永年間(1521~1528)年に建立したもので、三間社流造りの茅...
-

さいみょうじ(さんじゅうのとう、ろうもん、ほんどうないずし)西明寺(三重塔、楼門、本堂内厨子)
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 室町時代
- 栃木県益子町
- 建造物
西明寺は、のちに宇都宮氏の家臣となる益子氏が建立しました。紀氏を祖先に持つ益子氏は、本堂内には紀貫之の像も安置されて...
-

えんつうじおもてもん円通寺表門
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 室町時代
- 栃木県益子町
- 建造物
円通寺は良栄上人によって応永9年(1402)に創建された浄土宗旧名越派の総本山です。表門は唐様式四脚門形式、切妻造り茅葺き...
-

りょうごんじ(さんもんもくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう)楞厳寺(山門、木造千手観音立像)
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 鎌倉時代
- 室町時代
- 茨城県笠間市
- 建造物
- 彫刻
(山門) 屋根が禅宗様式の四脚門である。切妻造の茅葺屋根で、妻部分の刈り込みが鋭く、急勾配で厚みがある。柱間に扉や壁は...
-

もくぞうみろくぶつりゅうぞう木造弥勒仏立像
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 鎌倉時代
- 茨城県笠間市
- 彫刻
ヒノキ材の寄木造で、漆箔、玉眼嵌入である。螺髪が大きく、その各々に渦巻型の旋毛を刻む。肉髻が低く、地髪が張り、髪際は...
-

もくぞうやくしにょらいりゅうぞう木造薬師如来立像
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 鎌倉時代
- 茨城県笠間市
- 彫刻
ヒノキ材の寄木造で、漆箔、玉眼嵌入である。肉髻が大きく、頬がゆったりと柔らかで、衲衣は彫りが浅く美しく仕上げられてい...
-

かさまいなりじんじゃほんでん笠間稲荷神社本殿
- #087 かさましこ
- 有形文化財
- 重要文化財
- 江戸時代
- 茨城県笠間市
- 建造物
総ケヤキ材の素木による権現造で、屋根は本瓦形銅板で葺かれている。内陣(旧本殿)と外陣(旧拝殿)からなり、正面に向拝が...