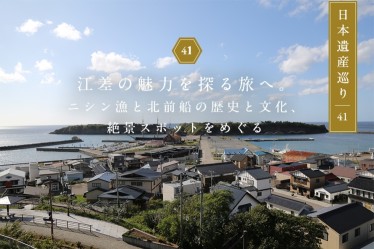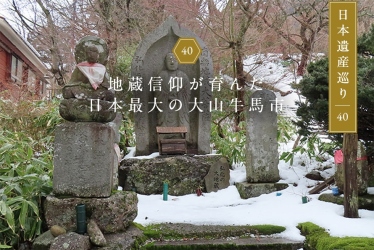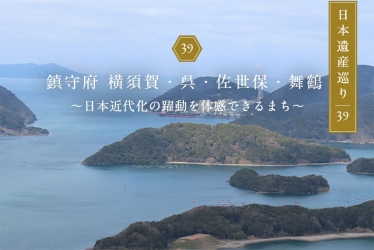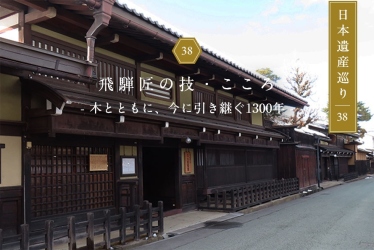かかあ天下-ぐんまの絹物語-STORY #002
テーマ
- 繊維・染料
時代
- 江戸
ストーリーSTORY
古くから絹産業の盛んな上州では、
女性が養蚕・製糸・織物で家計を支え、
近代になると、製糸工女や織手として
ますます女性が活躍した。
夫(男)たちは、おれの「かかあは天下一」と呼び、
これが「かかあ天下」として上州名物になるとともに、
現代では内に外に活躍する
女性像の代名詞ともなっている。
「かかあ」たちの夢や情熱が詰まった
養蚕の家々や織物の工場を訪ねることで、
日本経済を、まさに天下を支えた
日本の女性たちの姿が見えてくる。
女性が養蚕・製糸・織物で家計を支え、
近代になると、製糸工女や織手として
ますます女性が活躍した。
夫(男)たちは、おれの「かかあは天下一」と呼び、
これが「かかあ天下」として上州名物になるとともに、
現代では内に外に活躍する
女性像の代名詞ともなっている。
「かかあ」たちの夢や情熱が詰まった
養蚕の家々や織物の工場を訪ねることで、
日本経済を、まさに天下を支えた
日本の女性たちの姿が見えてくる。
上州の農家には、大切にしまわれてきた絹の着物が眠っている。代々の女たちが、蚕を育て、糸をひき、布に織り、着物に仕立てた、晴れ着や婚礼衣装である。
すべての技術は母から娘へ、地域の女達から少女達へと脈々と継承された。上州の女たち(かかあ)は、この養蚕・製糸・織物の力で家計を支え、家族の衣をつくった。
男たち(夫)は、この働き者の女たちを「おれのかかあは天下一」と自慢し、上州名物は「かかあ天下」となった。
美しい絹が織りなされる物語をたどると、日本独特の繊細なモノづくり文化とともに、誇りをもって家を支えた上州の女たちの姿が見えてくる。
すべての技術は母から娘へ、地域の女達から少女達へと脈々と継承された。上州の女たち(かかあ)は、この養蚕・製糸・織物の力で家計を支え、家族の衣をつくった。
男たち(夫)は、この働き者の女たちを「おれのかかあは天下一」と自慢し、上州名物は「かかあ天下」となった。
美しい絹が織りなされる物語をたどると、日本独特の繊細なモノづくり文化とともに、誇りをもって家を支えた上州の女たちの姿が見えてくる。
機(はた)の音、製糸の煙、桑の海
絹は、蚕という虫が作る繭から作られる。蚕は繊細な虫で、「お蚕こさま」と呼ばれ、子どものように、家の中で大切に育てられた。蚕の世話は、家の中を切り盛りする女たちの重要な仕事である。特に、成長期には寝る間を惜しんで蚕に桑の葉を食べさせなければならない。女たちは、蚕の世話、他の農作業、食事作りと休む間もなく働き、農家の働き手の中心として活躍した。
そして、幕末から明治へ、上州が群馬県と変わる頃、絹が主要な輸出品として外貨獲得の切り札となると、県内の養蚕・製糸・織物はますます盛んになった。明治の文豪、徳冨蘆花は当時の群馬県の様子を「機はたの音、製糸の煙、桑の海」*と詠んでいる。この時代の流れに乗って、上州の女は益々活躍の場を広げるのである。
*徳冨蘆花の随筆「上州の山」明治32年
そして、幕末から明治へ、上州が群馬県と変わる頃、絹が主要な輸出品として外貨獲得の切り札となると、県内の養蚕・製糸・織物はますます盛んになった。明治の文豪、徳冨蘆花は当時の群馬県の様子を「機はたの音、製糸の煙、桑の海」*と詠んでいる。この時代の流れに乗って、上州の女は益々活躍の場を広げるのである。
*徳冨蘆花の随筆「上州の山」明治32年
農家の財布の紐はかかあが握るべし
明治5年「富岡製糸場」が創業し、全国から少女たちが製糸工女として、また地域からは大量の繭が原料として、富岡に集められた。このような時、片品村の養蚕農家に嫁いだ「永井いと」は夫、紺周郎とともに繭増産のための養蚕技術の改良に挑み、夫亡き後もその意志を継いで、遂には永井流養蚕法の伝習所を設立した。いとは自ら教壇に立ち、講義の中で「農家の財布の紐はかかあが握るべし」と説いたという。農家の現金収入源である養蚕で、女性が活躍していたからこその言葉である。
邑ニ養蚕セザルノ家ナク製絲セザルノ婦ナシ
やがて、女たちは養蚕や繭作りだけでなく、繭から糸を繰り出す技術(座繰り繰糸)にも磨きを掛けていった。このような農家は、組合製糸という形で共同して生糸を販売するようになり、糸の品質でも、生産量でも器械製糸に劣らず、日本の経済を支える存在となった。
組合製糸を代表する甘楽社の碑には、「邑ニ養蚕セザルノ家ナク製絲セザルノ婦ナシ(村で養蚕をしていない家はなく、製糸をしていない女はいない)」とあり、まさに上州の女たち(かかあ)の活躍が印されている。彼女たちは、生糸を売って現金収入を得る傍ら、自家用の糸を少しずつ確保し、機織りをし、自分や家族の晴れ着を仕立てることも忘れなかった。そして、その着物と技術とを代々引き継いでいくのである。
西の西陣、東の桐生
日本製の生糸が世界を席巻するなかで、また、絹織物も発展していった。桐生は江戸時代から「西の西陣、東の桐生」と言われるように高級な絹の織物産地として知られていた。この桐生を支えたのも機織り女と呼ばれた周辺の村から集まった女たちであり、織物を伝えた白滝姫を祭る神社には、多くの機織り女が、織物の上達を願ってお参りした。
明治に入るとこの桐生の町並みには、ノコギリ型の屋根が特徴的な織物工場が数多く建てられていった。その中でさらに多くの女たちが織手として活躍した。また、撚糸*、染色、機拵え**にも女性たちが従事した。彼女たちが仕事の合間に外食をしたり銭湯に行ったり、お気に入りの着物や、時には洋服を着て歩いたりした町には、女性たちが活躍した足跡、商家や工場の町並み、その奥には寄宿舎や銭湯もしっかりとのこっている。桐生はそんな近代の女性たちの生活をずっと見つめてきたのである。
*織物の種類に合わせて糸によりをかける作業。
**紋織りのための準備作業。
現代の群馬にも、日本の絹織物の技術や文化が受け継がれている。農家の女性たちが生産に励む傍ら、自分や大切な家族のためつくった着物は、今でも大切に保存されている。織物の桐生には現在でも熟練の女性職人が働く現役の工場がある。日本伝統の美しい着物を着ること、そして懐かしい農家や織物の町並みを訪ねることで、日本を支えてきた「かかあ」たちの心に触れることが出来る。
「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」は、家族と地域を、そして日本を支えてきた女性「かかあ」たちの姿を、実際に、蚕に触れたり、繭から生糸をひいたり、絹布を織ったりして、体感していく物語である。
明治に入るとこの桐生の町並みには、ノコギリ型の屋根が特徴的な織物工場が数多く建てられていった。その中でさらに多くの女たちが織手として活躍した。また、撚糸*、染色、機拵え**にも女性たちが従事した。彼女たちが仕事の合間に外食をしたり銭湯に行ったり、お気に入りの着物や、時には洋服を着て歩いたりした町には、女性たちが活躍した足跡、商家や工場の町並み、その奥には寄宿舎や銭湯もしっかりとのこっている。桐生はそんな近代の女性たちの生活をずっと見つめてきたのである。
*織物の種類に合わせて糸によりをかける作業。
**紋織りのための準備作業。
現代の群馬にも、日本の絹織物の技術や文化が受け継がれている。農家の女性たちが生産に励む傍ら、自分や大切な家族のためつくった着物は、今でも大切に保存されている。織物の桐生には現在でも熟練の女性職人が働く現役の工場がある。日本伝統の美しい着物を着ること、そして懐かしい農家や織物の町並みを訪ねることで、日本を支えてきた「かかあ」たちの心に触れることが出来る。
「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」は、家族と地域を、そして日本を支えてきた女性「かかあ」たちの姿を、実際に、蚕に触れたり、繭から生糸をひいたり、絹布を織ったりして、体感していく物語である。
 左上:中之条町六合赤岩伝統的建造物群保存地区/右上:永井流養蚕伝習所実習棟/左下:旧小幡組製糸レンガ造り倉庫/右下:甘楽町の養蚕・製糸・織物資料
左上:中之条町六合赤岩伝統的建造物群保存地区/右上:永井流養蚕伝習所実習棟/左下:旧小幡組製糸レンガ造り倉庫/右下:甘楽町の養蚕・製糸・織物資料
| 【かかあ天下 関連情報サイト】 |
|---|