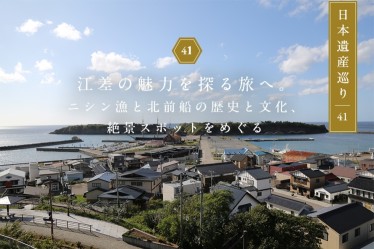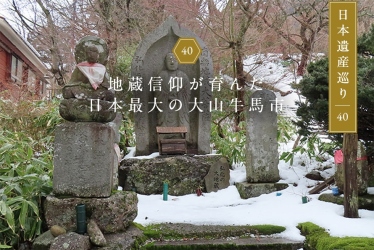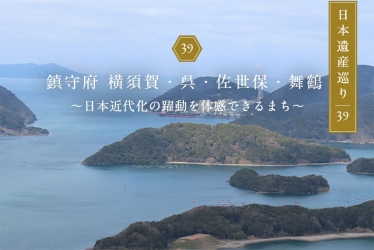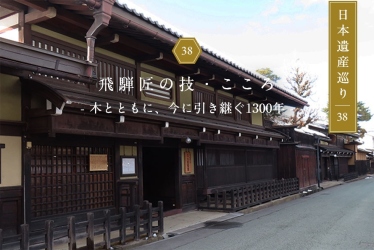灯(あか)り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~STORY #004
テーマ
- 海・水辺
- 祭礼
時代
- 江戸
ストーリーSTORY
日本海文化の交流拠点である能登半島は
独自の文化を育み、
数多くの祭礼が行われてきた。
その白眉はキリコ祭りと総称される灯籠神事。
夏、約200地区で行われ、能登を照らし出す。
日本の原風景である素朴な農漁村で
神輿とともに、最大で2トン、
高さ15mのキリコを担ぎ上げ、激しく練り回る。
祇園信仰や夏越しの神事から発生した祭礼が、
地区同士でその威勢を競い合う中で
独特な発展をし、
そしてこれほどまでに
灯籠神事が集積をした地域は唯一無二。
夏、能登を旅すれば
キリコ祭りに必ず巡り会えると言っても
過言ではなく、
それは神々に巡り会う旅ともなる。
独自の文化を育み、
数多くの祭礼が行われてきた。
その白眉はキリコ祭りと総称される灯籠神事。
夏、約200地区で行われ、能登を照らし出す。
日本の原風景である素朴な農漁村で
神輿とともに、最大で2トン、
高さ15mのキリコを担ぎ上げ、激しく練り回る。
祇園信仰や夏越しの神事から発生した祭礼が、
地区同士でその威勢を競い合う中で
独特な発展をし、
そしてこれほどまでに
灯籠神事が集積をした地域は唯一無二。
夏、能登を旅すれば
キリコ祭りに必ず巡り会えると言っても
過言ではなく、
それは神々に巡り会う旅ともなる。
灯(あか)り舞う半島 能登
日本列島のほぼ中央に位置する石川県。日本海に突き出た能登半島には、古来より大陸から様々な人々が渡来し、文化や技術がもたらされた。能登半島は「海の道」が主要交通路だった時代には、日本海を介して各地との交流が盛んに行われ、いわば、「日本海文化」の交流拠点としての役割を担っていた。
様々な文化を受け入れつつも、半島という地理的閉鎖性によって、独自の文化を育んできた能登には、今も、祭礼を始めとする貴重な民俗行事が受け継がれ、「民俗の宝庫」、「祭りの宝庫」と呼ばれている。6件の重要無形民俗文化財を含め、84もの指定無形民俗文化財が存在する。能登全体の人口約20万人という中で、民俗行事がひしめき合い、古からの伝承が色濃く残る神聖な空間を作り出している。
様々な文化を受け入れつつも、半島という地理的閉鎖性によって、独自の文化を育んできた能登には、今も、祭礼を始めとする貴重な民俗行事が受け継がれ、「民俗の宝庫」、「祭りの宝庫」と呼ばれている。6件の重要無形民俗文化財を含め、84もの指定無形民俗文化財が存在する。能登全体の人口約20万人という中で、民俗行事がひしめき合い、古からの伝承が色濃く残る神聖な空間を作り出している。
能登の祭礼の白眉は、「キリコ祭り」と総称される灯籠神事。キリコとは、切子きりこ灯とう篭ろうを縮めた呼び名であり、直方体の形をした山車だしの一種で、担ぎ棒が組み付けられている。キリコ祭りは、少なくとも江戸時代には存在し、能登の人々の生活に溶け込んで、今なお盛んに行われている伝統行事である。
キリコ祭りは、夏の約3ヶ月間、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町の3市3町合計約200もの地区で行われ、夜になると、キリコに灯がともり、浮かび上がった大書の墨字や武者絵が幻想的な空間を醸し出す。あたかも、夏、キリコが能登全体を照らし出しているかのようである。日本の原風景である素朴な農漁村で、漆や彫刻など意匠を凝らした多数のキリコが神輿のお供をしながら練り回るさまは、まさに豪華絢爛な祭礼絵巻である。
キリコ祭りと総称されているものの、それぞれの祭りを見ると全く多種多様である。キリコの数、形状、祭礼の行程などそれぞれに卓越した特徴があるので、いずれか一つを観れば、キリコ祭りの大要が掴めるというものではない。したがって、一つに留まらず、複数のキリコ祭りを「ラリー」するのもまた一興である。
キリコ祭りは、キリコを担いでいる一部の住民だけではなく、集落の住民皆が祭礼を楽しんでいる点に注目しなければならない。祭り当日、集落の家々は玄関、道沿いの窓を開け放ち、親類や知人を招待して盛大にごちそうをし、親交を結び合う「ヨバレ」の慣行が今も行われている。集落全体が熱気を帯びるキリコ祭りは、都会に出た者が、正月や盆に帰省しなくても、キリコ祭りには必ず帰ってくるというくらいである。
祇園信仰や夏越しの神事から発生したキリコ祭りが、集落間で伝播し、そのうち集落同士でその威勢やキリコの大きさ、装飾、数を競い合う中で独特の発展をしたと言われている。ただ、200ものキリコ祭りがなぜ今なお存在するのか。半島という地理的閉鎖性によって、自ずと狭い範囲内での交流となり、均質的な空間を作り出したというだけではない。「能登はやさしや土までも」・・・土まで優しい、いわんや人はどれだけかという意味が込められた能登の人々の温かさを表す言葉があるが、そういった「こころ」が神事・祭礼に対する熱心さとなって深く関わっているのである。
そして、これほどまでに灯籠神事が集積をした地域は全国を見ても唯一無二。夏、能登を旅すればキリコ祭りに必ず巡り会えると言っても過言ではなく、それはキリコが供奉ぐぶする神々に巡り会う旅ともなるのである。
キリコ祭りと総称されているものの、それぞれの祭りを見ると全く多種多様である。キリコの数、形状、祭礼の行程などそれぞれに卓越した特徴があるので、いずれか一つを観れば、キリコ祭りの大要が掴めるというものではない。したがって、一つに留まらず、複数のキリコ祭りを「ラリー」するのもまた一興である。
キリコ祭りは、キリコを担いでいる一部の住民だけではなく、集落の住民皆が祭礼を楽しんでいる点に注目しなければならない。祭り当日、集落の家々は玄関、道沿いの窓を開け放ち、親類や知人を招待して盛大にごちそうをし、親交を結び合う「ヨバレ」の慣行が今も行われている。集落全体が熱気を帯びるキリコ祭りは、都会に出た者が、正月や盆に帰省しなくても、キリコ祭りには必ず帰ってくるというくらいである。
祇園信仰や夏越しの神事から発生したキリコ祭りが、集落間で伝播し、そのうち集落同士でその威勢やキリコの大きさ、装飾、数を競い合う中で独特の発展をしたと言われている。ただ、200ものキリコ祭りがなぜ今なお存在するのか。半島という地理的閉鎖性によって、自ずと狭い範囲内での交流となり、均質的な空間を作り出したというだけではない。「能登はやさしや土までも」・・・土まで優しい、いわんや人はどれだけかという意味が込められた能登の人々の温かさを表す言葉があるが、そういった「こころ」が神事・祭礼に対する熱心さとなって深く関わっているのである。
そして、これほどまでに灯籠神事が集積をした地域は全国を見ても唯一無二。夏、能登を旅すればキリコ祭りに必ず巡り会えると言っても過言ではなく、それはキリコが供奉ぐぶする神々に巡り会う旅ともなるのである。
| 【灯(あか)り舞う半島 能登 関連情報サイト】 |
|---|