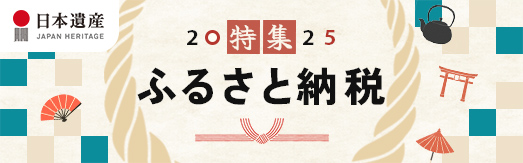「なんだ、コレは!」 信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化STORY #026
みどころspot
-

しらさぎ森林公園(花菖蒲)
広い菖蒲園や芝生広場、遊園施設を備えた展望広場などが整備され、人と自然のふれあいを目的とした憩いの森林公園として親しまれている「しらさぎ森林公園」。
約2万株の菖蒲が植えられた花菖蒲園は、色とりどりの菖蒲の花が咲きみだれ、開花に合わせた6月中旬から6月下旬まで「花菖蒲まつり」が開催されることから、毎年多くの方が花を楽しみに訪れています。
夜には花菖蒲の上をホタルが飛びかい、幻想的な雰囲気に包まれます。
祭りの期間中はフォトコンテストも開催します。花菖蒲見頃:6月中旬~7月上旬
花菖蒲まつり開催日:6月中旬~6月下旬新潟県三条市矢田727/しらさぎ森林公園 https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/events/event_info/2260.html 問い合わせ先:0256-34-5605 花菖蒲まつり実行委員会事務局(三条市役所営業戦略室 観光係) 続きを読む
-

星峠の棚田(越後松代棚田群)
十日町市を代表する棚田です。
大小様々な棚田約200枚がまるで魚の鱗のように斜面に広がっています。
雲海が発生し、水鏡が輝くベストシーズンには、その美しい風景を眺めようと全国各地から多くのカメラマンや観光客がこの地を訪れています。
四季折々・朝昼晩と様々な顔を見せてくれる星峠の棚田は、十日町市に点在する棚田の中でも最も人気がある棚田スポットです。十日町市峠 025-597-3442 https://www.tokamachishikankou.jp/natural/tanada/hoshitoge/ 続きを読む
-

美人林
松口の丘陵に樹齢約100年ほどのブナの木が一面に生い茂り、そのブナの立ち姿がとても美しいことから「美人林」と呼ばれるようになりました。
大正末期、木炭にするためすべて伐採され裸山になりました。
ところが翌年、この山のブナの若芽が一斉に生えだし、ブナ林が野鳥の生息地として見直され、美人林が保護されるようになりました。
全国から写真愛好家が集まる、人気の観光スポットです十日町市松之山松口1712-2付近 025-597-3442 https://www.tokamachishikankou.jp/bijinbayashi/ 続きを読む
-

節季市(チンコロ市)
冬期間の副業として、農家の人々が竹やわらなどで作った生活用品や民芸品を持ち寄り開かれる市として、江戸時代から始まったと言われる歴史ある市です。
毎年1月10日、15日、20日、25日に市内の諏訪町で開催され、通りには竹細工・わら細工などの民芸品や漬物、乾物、お菓子などを売る約50軒ほどの露店が立ち並びます。
その中でも縁起物の「チンコロ」が一番の人気です。毎年、チンコロを売る店の前には長蛇の列ができ、あっというまに売り切れてしまいます。
節季市は、別名「チンコロ市」とも呼ばれ、親しまれています。025-757-3100 http://www.city.tokamachi.lg.jp/kanko/K001/K006/1480582367129.html 続きを読む
-

「大地の芸術祭」の里(十日町市・津南町)
3年に1度開催される「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の舞台となる、越後妻有地域(新潟県十日町市・津南町)を「大地の芸術祭の里」と呼んでいます。
ここでは、1年を通して、地域に内在するさまざまな価値をアートを媒介として掘り起こし、その魅力を高め、世界に発信し、地域再生の道筋を築くことを目指しています。
その成果発表の場となるのが、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」です。
(画像:草間彌生「花咲ける妻有」 Photo by Osamu Nakamura)025-761-7767 http://www.echigo-tsumari.jp/ 続きを読む