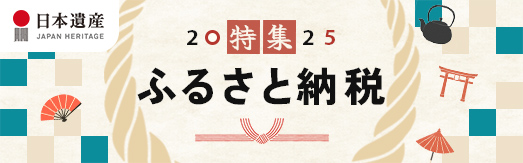関門“ノスタルジック”海峡~時の停車場、近代化の記憶~STORY #052
みどころspot
-
![ホーム・リンガ商会[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_4fbd2a356cc02dfed8a0fa08643997a1c195ced9.jpeg)
ホーム・リンガ商会[構成文化財]
明治の日本の貿易に大きく貢献した、イギリス人貿易商が長崎で設立した会社「ホーム・リンガ商会」の系譜を受け継ぐ淡い色使いが印象的な建築物。
建物正面には「HOLME RINGER」と白い壁に白い文字で書かれています。海側から見える壁には青い文字で大きく「RINGER」と書かれていて海上からでも見やすいように工夫されています。福岡県北九州市門司区港町9-9 https://www.japanheritage-kannmon.jp/bunkazai/index.cfm?id=6 続きを読む
-
![19世紀末から20世紀初期にかけてドイツやオーストラリアで広まった様式―セセッションー旧秋田商会ビル[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_0bca268ed02e462200f01d977f3330006c6c676e.jpeg)
19世紀末から20世紀初期にかけてドイツやオーストラリアで広まった様式―セセッションー旧秋田商会ビル[構成文化財]
国内最初期の鉄筋コンクリート造事務所建築だと言われ、施工は大阪の駒井組が請け負いました。現場監督は秋田寅之介の親族でのちに関門商事に勤める新富直吉。設計者は西澤忠三郎が担当したと最近になって判明し、和風建築部分は京阪神で活躍していた宮大工の後藤柳作が手がけたと推測されています。
西澤忠三郎は技手(技師の下に属する技術者)として文部省に雇われ、九州大学を建設していた事務所に所属していましたが、遼東半島につくられた関東州の関東都督府に移り大正期まで勤め、帰国しています。
下関の歴史的建造物には建築デザインの移り変わりが如実に表れています。明治期の古典主義株式から脱却していこうとする大正時代の過渡期の建築。旧秋田商会ビルには明治期の様式建築が残りながら当時最新の意匠上の要素が見られ、変化しつつあるのがわかります。街歩きを楽しみながらデザインの変遷にもぜひ注目してください。
山口県下関市南部町23-11 083-231-4141 https://www.japanheritage-kannmon.jp/bunkazai/index.cfm?id=29 続きを読む
-
![日本を代表するオペラ歌手・藤原義江の父N・B・リードが支配人として居住―藤原義江記念館(旧リンガー邸)[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_7c38ceea838820dd19fad761efd585aeb3f5938d.jpeg)
日本を代表するオペラ歌手・藤原義江の父N・B・リードが支配人として居住―藤原義江記念館(旧リンガー邸)[構成文化財]
当時の外国人居留者は景色の良い高台を好み、家を建てていました。この建物も関門海峡を一望できる高台にあり、全ての部屋に大きな外開きの窓が設けられています。室内からはきっと日々刻々と変わる雄大な景色を楽しんだことでしょう。
建物は鉄筋コンクリート造です。滑らかな平面や小さい庇付きの矩形窓などの装飾要素を排除した外観や、室内の直線を基調としたデザインは、昭和初期の特徴で、歴史的装飾を一切排除したモダニズム建築です。
2階は漂泊者のアリア記念室で、藤原義江の一生を描いた下関市出身の古川薫の直木賞受賞作「漂泊者のアリア」にちなんでいます。居室に置かれた机や小物、書籍は実際に藤原義江が使っていたものです。2階3階は現在は立ち入り禁止となっています。
山口県下関市阿弥陀寺町3-14 083-234-4015 https://www.japanheritage-kannmon.jp/bunkazai/index.cfm?id=34 続きを読む
-
![杤木ビル[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_0d8b34c2a5ca1b0cbcc5d9755d40d0733b431c1d.jpeg)
杤木ビル[構成文化財]
洞海湾を背にしてビルが建ち、前面道路と背後の岸壁線に挟まれた立地からか、台形の形状になっています。
ユニークなのは表側(道路側)と裏側(海岸側)の2カ所に玄関が備わっているところ。しかも表側に対して、裏側のほうが大きく立派な玄関が設けられているのです。後者には風除室まであるので、どうやら海側の玄関が正式なものだと考えられます。杤木商事の商売が陸側にではなく、海側に重点が屋かれていたことが伺える造りです。
ビル全体の形状は街中でよくみられる単純なものですが、玄関部をはじめ、ビルの細部に大正中期のデザインの特徴が認められます。明治期の細やかな装飾を多用するデザインから昭和初期のシンプルなデザインへの橋渡し的な役割が感じられる貴重な例です。
福岡県北九州市若松区本町1-15-10 https://www.japanheritage-kannmon.jp/bunkazai/index.cfm?id=22 続きを読む
-
![九州鉄道記念館(旧九州鉄道本社)[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_64f5e06eb8effea47d2137b561729834c514cabd.jpeg)
九州鉄道記念館(旧九州鉄道本社)[構成文化財]
九州鉄道記念館は、本館、車両展示場、ミニ鉄道公園、前頭部展示場の4つのエリアで構成されています。
本館は、今も残る数少ない明治期の煉瓦建造物で、外観で注目すべきなのが、1階と2階の間に施された胴蛇腹です。煉瓦を斜めに積む「矢筈(やはず)積み」と小端のいなづま蛇腹など2本の蛇腹を取り入れて、意匠的効果を高めています。
館内には九州の鉄道の歴史を紹介する常設展示コーナーがあり、歴代の名列車「つばめ」を紹介する「つばめコーナー」が人気を集めています。
車両展示場には、明治期に九州鉄道で活躍した9600型蒸気機関車やC59型蒸気機関車をはじめとして、寝台列車や石炭車などさまざまな車両が展示されているので、鉄道ファンは見逃せません。
「キハ42055号気動車(キハ07形41号気動車)」が重要文化財に指定されました!
「キハ42055号気動車(キハ07形41号気動車)」昭和初期に流行した流線形の車体や内装の多くが製造当時の姿をとどめているとともに機械式の変速装置が残る唯一の同形車両で気動車としては初の重要文化財となりました。
〒801-0833 福岡県北九州市門司区清滝2丁目3番29号 093-322-1006 http://www.k-rhm.jp/ 続きを読む